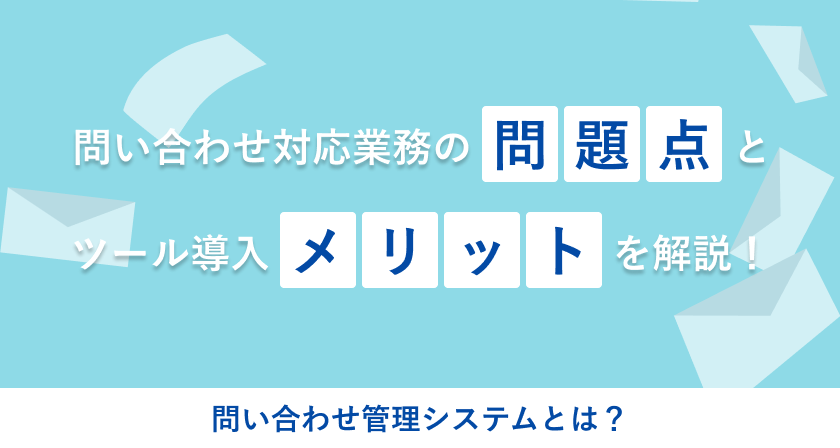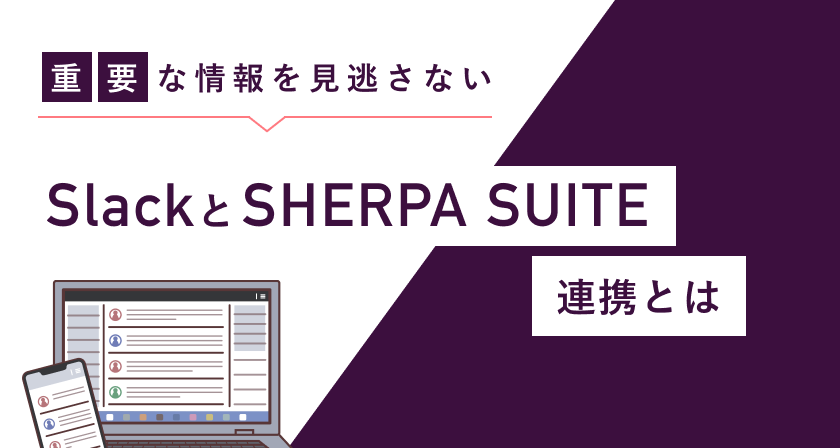システム運用コストとは
システム運用コストとは、ITシステムを継続的に稼働させるために必要な経費のことです。このコストには、インフラ運用、ソフトウェアライセンス、保守契約、人件費などが含まれます。特に、運用におけるトラブル対応やシステムアップデートなどの定期的な作業もコストに影響します。これらの費用は企業のIT予算に大きな影響を与えるため、適切なコスト管理が求められます。クラウドの普及により、オンプレミス型の運用に比べ柔軟なコスト管理が可能になっていますが、計画性がない場合は無駄な出費につながるリスクもあります。システム運用と聞いて思い浮かべるものは、人によって様々だと思います。実際、システムを正常に動作させるための定常作業からクリエイティブな運用法の考察に至るまで、システム運用が内包する概念は数多いのですが、ビジネスの観点からすれば、システム運用は「投資」です。もちろん、システム開発も「投資」となります。
システム開発においては、必ずコストや期間などが見積もられ、投資効果、あるいは費用対効果が十分であると判断された場合にのみプロジェクトが動き出します。
つまり、システム開発を投資と見なすことは当然であるとも言えるでしょう。
しかし、システム運用はどうでしょう。大抵の人が運用コストは“必要経費”だと思っているのではないでしょうか。
そもそも企業における「運用コスト」とは?
「運用コスト」とは、事業やシステムを継続的に運用・維持するために発生するすべての費用のことです。イニシャルコスト(初期費用)が設備購入やシステム導入など最初に一度だけ発生する費用であるのに対し、運用コストは事業を続ける限り定期的に支払い続ける費用の総称です。運用コストは「ランニングコスト」と呼ばれることもあり、人件費や設備の維持費、光熱費、在庫管理費など広範囲に及びます。
運用コストを適切に管理・削減できれば、その分を新たな事業投資や従業員への還元に充てることができ、競争力強化につながります。一方で運用コストの増大を放置するとキャッシュフローを圧迫し、経営の安定性を損なう恐れがあります。そのため「運用コストの最適化(適正な水準にコントロールすること)」が企業経営では重要視されているのです。
運用コストの内訳
運用コストにはさまざまな費用項目が含まれますが、大きく分けると固定費と変動費の2種類に分類できます。ここでは、運用コストを構成する主な費用項目について詳しく見てみましょう。
固定費と変動費の分類
・固定費: 業績や生産量に関わらず毎月・毎期一定額が発生するコストです。例えば、オフィスや工場の賃借料、設備のリース料、正社員の基本給、保守契約費などが該当します。固定費は売上がゼロでも支払いが発生するため、事業規模に見合った適正な水準に抑えることが重要です。固定費が過大だと、売上減少時に利益が一気に悪化するリスクがあります。
・変動費: 業績や取引量に応じて増減するコストです。製品の原材料費、販売数量に比例する物流費や包装費、外注費、時間外労働手当などが代表例です。変動費は売上や生産に連動するため、収入が増えれば増加しますが、逆に業績悪化時には自然と減る特性があります。変動費の割合が高いと景気変動に対する柔軟性は高まりますが、変動費そのものの単価を下げる努力(仕入れ先の見直し等)も利益率改善には重要です。
主な運用コストの種類
※表: 主な運用コストの項目と例
| コスト項目 | 内容(例) | 特徴(固定/変動) |
|---|
| 人件費 | 給与・賞与、社会保険料、福利厚生費など。 | 多くは固定費(基本給など)。残業代は変動要素。 |
| 設備費 | 減価償却費、機器の保守・修理費、備品購入費など。 | 減価償却費等は固定費。修理費・消耗品費は変動費。 |
| IT・クラウド費用 | ソフトウェアライセンス、クラウド利用料、保守費用。 | 月額定額利用料は固定費。利用量に応じた従量課金部分は変動費。 |
| 物流コスト | 配送運賃、倉庫料、梱包資材費、燃料費など。 | 取扱数量や距離に応じて増減する変動費。 |
・人件費: 従業員に支払う給与や賞与、社会保険料などの費用です。人件費は多くの場合固定費に分類され、運用コストの中でも大きな割合を占めることが一般的です。例えば、正社員の基本給や福利厚生費は毎月固定で発生します。ただし、残業代や臨時雇用者の賃金などは業務量に応じた変動費的性格も持ち合わせます。人件費は企業の存続と成長に欠かせない人材への投資ですが、売上規模に対して過剰な人員を抱えると負担増につながるため、適正な人員配置が求められます。
・設備費: 事業運営に必要な設備や機器にかかる費用です。具体的には機械装置の減価償却費、メンテナンス・修理費、オフィスや店舗の什器備品費などが該当します。設備費のうち、減価償却費やリース料は毎期定額発生するため固定費ですが、修理代や消耗部品の購入費などは故障状況や使用状況によって変動します。また、老朽化した設備を使い続けると維持費(修繕費やエネルギー消費)が高くなりがちで、新しい設備への更新タイミングも運用コストに影響します。
・ITシステム・クラウド運用コスト: 現代の企業運営では、IT関連の費用も運用コストの重要な構成要素です。業務システムの保守費用、ソフトウェアのライセンス料、クラウドサービスの利用料、サーバーやネットワークの運用費用などが含まれます。例えば、自社サーバーを運用する場合の電気代や保守契約費用、セキュリティ対策費用もこれに当たります。クラウドサービスを利用している場合は、月額利用料や従量課金制のリソース費用が発生します。ITコストは一見すると技術部門だけの費用に思えますが、業務全般の効率と密接に関わるため、中小企業でも全社的に注視すべき運用コストです。
「開発」と「運用」のコスト
「開発」と「運用」のコストを考えてみると、当然最初にかかるのは開発コストです。要件定義、設計、実装、テストの段階では、当然ながらバリュー(リターン-投資額)はマイナスです。システムが稼働を開始することをカットオーバーと言いますが、カットオーバーの時点では投資額が最も膨れ上がり、バリューがまったくない状態になっています。
つまり、開発コストを回収し利益を出すためには、カットオーバー後の「運用・保守フェーズ」で頑張らなくてはなりません。投資の観点から言えば、このフェーズで損益分岐点を超え、次の投資までにどれだけのリターンを得られるかが重要になります。
このように考えると、「開発コスト」と「運用コスト」は共に重要であることがわかります。開発コストが膨大であれば、回収までに時間がかかります。運用コストが増大すれば、回収のスピードが遅くなります。そして、システムには「利用期間」という制約があります。利用期間中にコストが回収できなければ、そのプロジェクトは失敗の烙印を押されるでしょう。つまり、運用コストを「開発が終わった後の単なるルーチンワーク」のように考えてはいけません。投資活動の成否を決める重要な要因だと捉えるべきです。
なお、「開発のコストを圧縮すると運用コストが跳ね上がることがある」などと言われることがありますが、この場合に発生しているのは、急造のシステムが使いにくかったり、不具合が頻発するといった、開発フェーズの“後始末”としてのコストです。システムを運用するために必要なランニングコストとは明確に異なりますので、注意しましょう。
コストの内訳と課題
システム運用コストは、主に直接コストと間接コストに分類されます。
直接コストには、ハードウェアの維持費やライセンス料が含まれ、間接コストには、運用スタッフの教育やシステム障害時の対応費用などが含まれます。また、デジタルトランスフォーメーション(DX)が進む中で、旧来のシステムから新システムへの移行費用も新たな課題となっています。特に、複数のツールを導入した結果、管理が煩雑になり運用負荷が増加するケースもあります。このような課題を解決するためには、ツールの統一やプロセスの自動化が必要です。
コスト削減と効率化のポイント
運用コストを削減するには、プロセスの効率化と自動化が鍵です。たとえば、監視ツールやITサービス管理(ITSM)ソリューションを導入することで、トラブル対応の迅速化や運用負荷の軽減が期待できます。また、クラウドサービスを利用することで、物理的なハードウェア維持費用を削減しつつ、リソースを柔軟にスケーリングできます。一方で、効果的な削減には現状のコスト構造を可視化し、不要な費用を見直すことが重要です。さらに、運用チームのスキル向上や外部リソースの活用も長期的なコスト効率化につながります。
当社が提供するSHERPA-IRとは
障害が発生すれば一刻を争って障害対応を行わなければなりません。
システム運用現場では障害対応手順などの操作に関する改善は割と行われていますが、運用全体の改善までは手が回らないのが悩みとなります。
障害発生から復旧完了までの間には様々なステップがあり、多くの現場では人手に頼ったリソースありきの運用をしているのが実情です。
しかも、その作業が煩雑で数が多くなってくると、急激に時間がかかりミスも多くなります。
この様な運用対応プロセス業務をSHERPA-IRで自動化すると、今までかかっていた時間と労力が大幅に簡略化され復旧作業を集中して行うことが出来ます。
また、同一障害のアラートが重複して出てしまう環境では、自動実行処理も重複して実行してしまう為、ジョブツールやRPAなどの自動処理ツールとの自動連携はできませんでした。
SHERPA-IRを使うと、同一アラートの集約処理後、処理実行の要不要判別をはじめ、発生時間帯やその他条件を考慮し、障害対応チケットを介して該当する自動化ツールと自動連携が可能となります。
こうしたオペレーションの自動化で、効率化・高品質化・コスト削減の3つを実現します。
SHERPA-IRについてはこちら